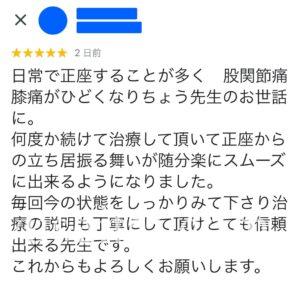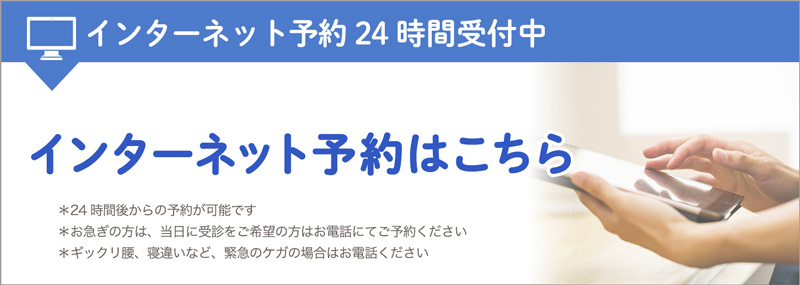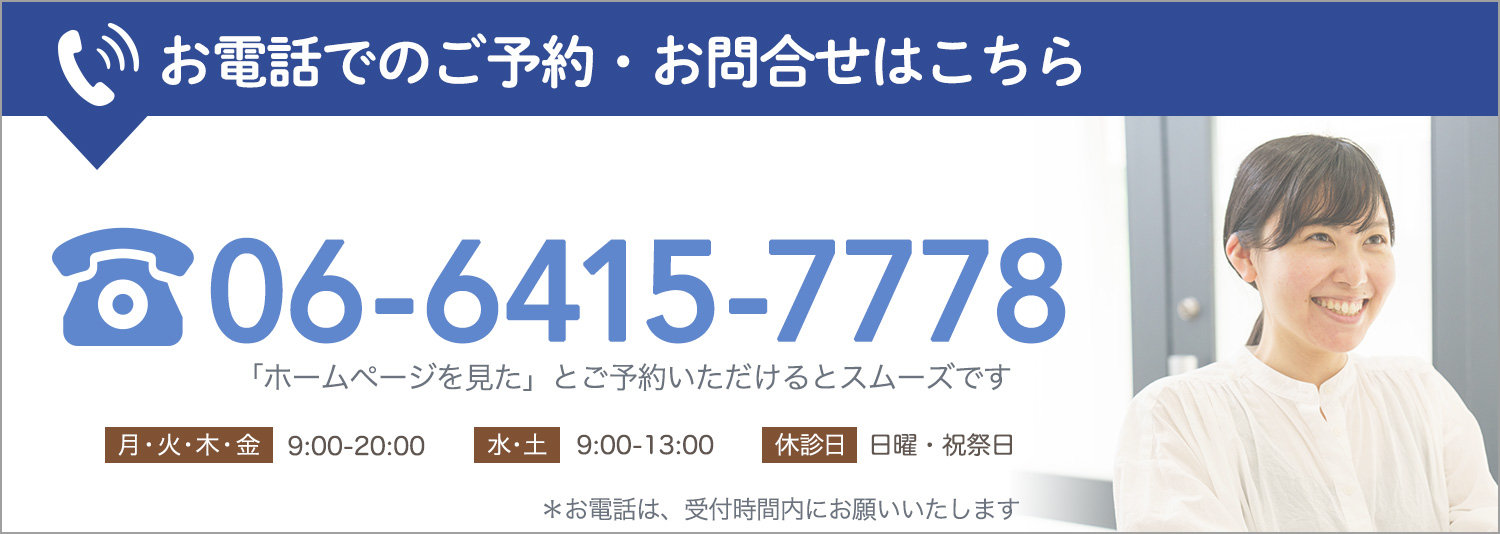「正座からの立ち居振る舞いがスムーズにできるようになりました」
「膝の痛みを気にせずに正座することができました」
茶道教室をなさっている女性患者さんから、お喜びの声を頂戴しました。
正座をすると膝が痛い…立ち上がることさえままならなかった女性患者さんの症例

こんにちは。
兵庫県尼崎市にあります、ちょう鍼灸整体院の曹(ちょう)です。
先日、当院へ膝の痛みで通院なさっていた女性患者さん(以下、Tさん)より、
「正座からの立ち居振る舞いが、随分楽にスムーズにできるようになりました」
という、お喜びの声を頂戴しました。
Tさんはこれまで茶道家として、茶道教室や100人規模の講演会を開催なさるなど、とても精力的に活動なさっている方です。

ですが、そんなTさんも来院当初は、
「膝が痛くて、正座からの立ち居振る舞いがうまくできない…」
「長時間正座をしていると膝が痛くてつらい…」
といったお悩みを抱えておられました。
仕事柄、正座をする機会が多く、膝の痛みで日頃の生活や仕事にまで支障をきたしてしまい悩んでおられたそうです。
そんな時にTさんの知人が当院へ通われていたことをきっかけに、これ以上ひどくなる前にとご紹介で来院くださいました。

それからは定期的に施術を継続し、今ではほとんど支障なく仕事へ打ち込むことができておられます。
実はその際、Tさんには施術だけでなく、ある対策方法についても合わせて取り組んでいただけるようお伝えしました。
それにより症状が早期に軽快したといっても過言ではありません。
では、その対策方法とはいったいどのような方法なのでしょうか?
今回のブログへ詳しくまとめさせていただきました。
もし正座をした後の膝の痛みでお困りでしたら、このブログ内容がきっとお役に立てると考えております。
お時間のある時に、ぜひ最後までご覧になってみてください。
正座で膝が痛む時に逆効果となり得る対策とは?

膝の痛みでご相談をいただく患者さんから、
「ネットで見つけた動画では〇〇が良いって言ってたんですけど、かえって痛みがきつくなってしまって…」
というお声をお聞きすることがあります。
少しでも良くなりたいという思いから、せっかく見つけた対処法を試してみたのに、かえって症状を悪化させてしまうのはつらいですよね。
もちろんそのようなすべての対処法が正しい・間違っているというわけではなく、当院ではその患者さんに合った方法を実践いただくことが大切だと考えております。
そこで、なるべくそのようなリスクを負わなくて済むよう、ここではまずは逆効果になり得る対策についてまとめました。
片側に体重をかける

よく膝の不調でお困りの方にお話を伺ってみると、
「膝に負担がかからないよう、なるべく反対の足に体重をかけるようにしています」
といったこともお聞きすることがあります。
例えば、公園でよく見かけるシーソーをイメージしていただけないでしょうか?
シーソーは左右対称に同じ重さの人が乗れば、バランスを維持できるかと思います。

ですが、片側ばかりに人が乗ると、バランスは一気に傾き出します。
これと似ていて、人の体も常に片側ばかりに体重をかけると、体のバランスは崩れやすくなってしまうのです。
バランスが崩れると、体はなんとか支えるためにどこかで余計な踏ん張りを効かせなくてはならなくなります。
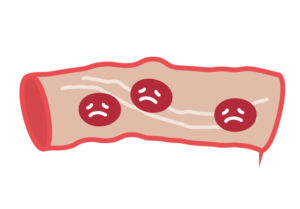
すると、踏ん張ることで硬くなった筋肉はホースを曲げた時のように、血の巡りを悪くしてしまうことに。
そして、その血液には栄養や酸素が豊富に含まれており、植物が肥料や水を必要とするように、筋肉や関節も柔軟性を保つために血液がとても重要なのです。
そのようなことからも、片側に体重をかけることは症状をより悪化させてしまう可能性があります。
膝を冷やす

今回のような膝の不調を起こすケースでは、基本的には温めて血の巡りを促すことが重要です。
膝に不調を起こす原因として多くの場合は、膝を支える周りの筋肉や組織が疲労を起こし、血の巡りが悪くなってしまうことが挙げられます。
例えば、自転車のチェーンも使い続けると、油切れや汚れが溜まることで動きが悪くなり、漕ぐのが大変になってしまいませんか?

膝も同じで、周りの筋肉や組織が疲労で硬くなったりすると、血の巡りが悪くなり本来の動きがスムーズにできなくなります。
そのような状態が続いた結果、膝は痛みや違和感などの不調を起こしてしまうのです。
ですので、自転車のチェーンも油をさせば良くなるように、膝まわりの筋肉や組織も温めることで血の巡りが良くなり回復を促すことができます。
そのようなことから膝を冷やす行為は、かえって症状を悪化させるリスクが伴うのです。

しかし、怪我による明らかな腫れや熱感・赤み・疼きなどの症状が見られる場合は、まず冷やすことを優先してください。
目安としては、15分ほど氷や氷嚢を使って冷やしてあげると良いかと思います。
これで少しずつ症状が落ち着けば、それ以降は温める方へ切り替えていただくことが好ましいです。
ですが、冷やしたにも関わらず一向に痛みが引かない、あるいは熱感や腫れが続き症状が悪化していく場合は、一度専門の医療機関を受診なさることをおすすめします。
安静にする

膝が痛いとこれ以上ひどくならないよう、安静になさる方もおられるかもしれません。
ですが、例えば粘土も放置すると乾いて硬くなってしまうように、体も安静にしすぎるとかえって血の巡りが悪くなり筋肉を硬くしてしまいます。
その結果、本来のスムーズな動きが失われることで、膝の不調へとつながってしまうのです。
正座からの立ち上がりで膝が痛む時におすすめする効果的対策

では、Tさんはどのようにして、このような膝の不調を克服することができたのか?
今回はTさんへお伝えした、実際の対策方法をご紹介させていただきました。
足を均等に揃える

まずお伝えしたのが、日頃からなるべく足を揃えていただくことです。
座る姿勢や立っている時の姿勢など、気づけば片側に体重をかけてしまこともあるかと思います。
そのような姿勢に気付いた際、足を均等に揃えていただくことを意識していただきました。
そうすることで体の傾きを防ぐことができ、なるべく良いバランスを維持することが可能になります。
お風呂に浸かる

お風呂に浸かり、全身を温めてあげることも効果的です。
お風呂で温まることで血の巡りが良くなり、筋肉も柔軟性を取り戻しやすくなります。
特に毎回の入浴をシャワーだけで済ます方は、最低でも3日に一回程度は、ぜひゆっくりと浸かる時間を作ってみてください。
そして、お風呂に浸かる際、お湯の温度や入浴時間も大切です。
40℃前後の湯船に10分程度浸かっていただくと、体が芯から温まりリラックス効果も高まります。
温度が高すぎたり長く浸かりすぎたりすると、かえって逆効果となることもありますのでお気をつけください。
軽い運動

安静にしすぎると血の巡りは悪くなってしまう傾向にあります。
ですので、日頃から軽い運動を取り入れることもおすすめです。
「でも、膝が痛いのに運動なんて…」
と心配になられた方も、どうかご安心ください。
もちろん可能であれば、軽いウォーキングなどといった運動を取り入れていただけると良いかと思います。
ですが、おっしゃる通り膝の痛みで歩くのさえ嫌になる時はありますよね。

そのような場合はお風呂上がりの体が温まった状態で、柔軟体操をするといったことでも構いません。
他にも足首をゆっくり回すなど、膝に関連するところを意識的に動かすだけでも、少しずつ筋肉の柔軟性を取り戻していくことができます。
正座をしても膝の痛みなくスムーズに動けるようになった女性患者さんの喜びの声
Tさんにも今回ご紹介させていただいた方法を取り組んでいただき、治療期間としては2ヶ月の間に6回の施術を受けていただきました。
その甲斐もあり、今では正座からの立ち居振る舞いもスムーズになり、お悩みだった症状も随分と軽減されたようです。
現在のTさんは、当院で月に一回ほどのメンテナンスを受けていただくことで、お体の良い状態を維持なさっておられます。
これからも快適な毎日をお過ごしいただけるよう、精一杯サポートさせていただきます。
実際にTさんからいただいたお声を下記にまとめております。
現在、同じようなお悩みを抱えている方の励みになれば幸いです。
日常で正座することが多く、股関節痛・膝痛がひどくなりちょう先生のお世話に。
何度か続けて治療して頂いて正座からの立ち居振る舞いが随分楽にスムーズに出来るようになりました。
毎回今の状態をしっかりみて下さり治療の説明も丁寧にして頂けとても信頼出来る先生です。
これからもよろしくお願いします。
【60代 女性 T様 神戸市在住】
正座をした後に膝が痛いとお悩みの際は当院までご相談ください

この度のブログでは、正座をした後の膝の痛みでお困りの方に向けて、実際の改善例を元に対策方法をご紹介させていただきました。
この方法を日頃から取り組んでいただくことで、正座をした後の膝の痛みを和らげる効果が期待できます。
ですが、取り組んでみたものの一向に良くならない時は、他の原因が考えられるかもしれません。
もしそのようなことでお困りの際は、当院までお早めにご相談ください。
きっとお悩みを解決するお力になれると考えております。
最後までご覧いただきありがとうございました。
【監修:鍼灸師 曹 将鎬(ちょう ちゃんほ)】